| �����EOB�̊F���R�ŏo������ԁX�̏Љ�R�[�i�[�ł� |
| ���N���b�N����Ƃ��ꂼ��̎R�̉Ԃ̏Љ�ڍׂփW�����v���܂��B |
���k�C����
��2012�N7���@�A�|�C�x�̉ԁ@���c�@���u(���a42�N��)�@�@
��2012�N7���@�g�����E�V�̉ԁ@�|���@��(���a39�N��)�A���c�@���u(���a42�N��)�@
��2010�N7���@���A��̉ԁi�P�F���x�j�@�����@�떾(���a43�N��)
��2010�N7���@���A��̉ԁi�Q�F�k�C�x�E���_�x�E����x�j�@�����@�떾(���a43�N��)
��2010�N7���@���A��̉ԁi�R�F�����P���E���ʊx�j�@�����@�떾(���a43�N��)
��2010�N7���@���A��̉ԁi�S�F���_�x�E�g�����E�V�R�j�@�����@�떾(���a43�N��)
��2009�N8���@�J���C�G�N�E�`�J�E�V�R�̉ԁ@�얼�@�^���@(���a62�N��)
��2009�N�V���@���R�n�̉ԁ@�|���@��(���a39�N��)�@�@�@������2009�N8��20�����e
��2007�N�V���@�k�C���̉ԁi���K�x�E�當���E�r���R�j�@�g��@���v(���a39�N��)
��2007�N�V���@�k�C���̉ԁi�x�X�g�E�X���[�l�C���[�j�@����@���i���a31�N���j
�����k���@�@
��2009�N�V���@�����A��̉ԁ@�얼�@�^��(���a62�N��)�@�@�@������2009�N8��17�����e
����M�z��
��2012�N7���@�ΑŎR�̉ԂQ�@�����@�떾(���a43�N��)�@�얼�@�^��(���a63�N��)
��2010�N7���@�ΑŎR�̉ԁ@�R�{�@�����@(���a36�N��)
��2009�N8���@�x�̉ԁ@�����@�떾�i���a43�N��)�@�@������2009�N8��17�����e
��2009�N8���@���x�̉ԁ@�|���@���i���a39�N���j�@�����@�떾�i���a43�N��)�@
���k�A���v�X��
��2013�N8���@������c���R�[�X�i���������`�u�i�������j�̉�
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�떾(���a43�N��)�@�얼�@�^��(���a63�N��)
��2010�N8���@���������̉ԁ@�����@�떾(���a43�N��)�@�얼�@�^��(���a62�N��)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������2010�N9��10�����e
��2010�N6���@�U���̏㍂�n�̉ԁ@�����@�M���i���a38�N���j�@�@������2010�N6��9�����e
���k����
��2009�N8���@���R�̉ԁ@�|���@��(���a39�N��)�@�@�@������2009�N9��24�����e
���q�}������
��2010�N10�`11���@�q�}�����̉ԁi���̂Q�j�@���c�@���u(���a42�N��)�@
��2009�N10�`11���@�q�}�����̉ԁ@���c�@���u(���a42�N��)
���u�[�^����
��2009�N7���@Meconopsis in Bhutan�@�����@��(���a33�N��)
****
|

 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
|
|
��2013�N8���@������c���R�[�X�i���������`�u�i�������j�̉�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�떾(���a43�N��)�@�얼�@�^��(���a63�N��)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������������@2013�N11��16�����e
���w�����R�s�x�2013�N8��2�`7���@���������R�s�i�Ԗؑ�k�s�E������c���j�Q��
�@�i�܂������j
��������c���R�[�X�Ƃ́A�k�A���v�X�̍����_�����̃u�i�������o������N�_�Ƃ��A�G�X�q�x�E����ܘY�x�E�h�H�x�E�o�Z�x���琼���������o�đ����x�֎���o�R���̑��́i�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�x�j�ł��B���āA�Ԗؑ�k�s���I������̉�����ŁA8��5���`7���ɂ����ĎO���R�����痠������c�����u�i������������܂����B������������G�X�q�����Ɍ�����������̎R�s�O�̃C���[�W�͐^���x�܂ł͊⍬����̗Ő��A����ܘY���ӂ͍��I�n�Ȃ̂ő����A���Ԕ����Ȃ����R�A���͊y���߂Ȃ����낤�ƌ������̂ł����B
�@�Ƃ��낪���ۂɕ����Ă݂�ƁA�^���x�܂ł̊�A�Ƀ~���}�_�C�R���\�E�A�C���I�g�M���Ȃǂ̉��F�̉ԁA�~���}�I�_�}�L�A�C���M�L���E�Ȃǂ̎��F�̉Ԃ��y���݂܂����B����ɎO�c�x��O�őf���炵�����Ԕ��ɑ������������グ�܂����B��k������������̎ΖʂɃ`���O���}�A�n�N�T���C�`�Q�A�c�K�U�N���̌Q�����炫�ւ��Ă��܂����B�O�c�x����̉��荻�I�n�ɂ̓R�}�N�T�̌Q�������X�Ɍ���܂����B�܂��A�c���Ō�̂��܂��͉G�X�q�x��̉G�X�q�l�\���r�̒r���̎���̃`���O���}�A�c�K�U�N���̌Q���ł����B�Ő������̎R�x�i�ςƓ����ʁA���R�A�����y���߂܂����B�R�s�O�̃C���[�W���S������܂����B�i�����j
��������ɂ͊܂܂ꂸ�A�܂��A�ʐ^�ɂ��B��܂���ł������A�����ܘY�x���ӂ̃J�[���ł́A���������Ԃ�̃R�o�C�P�C�\�E���A�����߂��ɖ��̒��������B�ꂵ�Ȃ���A�����낵���Ȃقǂ̃{�����[���ŎR�̎Ζʂ��s�����A���̐��̂��̂Ƃ͎v���܂���ł����B����̓t���[���ɐ����Ă��`���Ȃ��A�̊������ł��Ȃ����i���Ǝv���܂����B
�@�O���R���ŕ������b�ł́A2013�N�́A���N�Ɉ�x�K���R�o�C�P�C�\�E�̓�����N�����������ł��B�܂��A�V��?�W����{�̂P�J���Ԃɐ��ꂽ���͐��������Ȃ��A�J�̑����ăV�[�Y���̖��J���������Ƃ��B���ꂾ���ɉԂ��������炢�Ă���Ƃ����b�ł����B
�@���������ɂ́A�v�����A�}���킩��Ȃ�����ǎB�e�ړI�炵���A�̂Ȃ���̎R������R�Ƃ����l�������e�[�u���̈�p��w����Ă���������ł��܂����B�R�i�Ƃ��ɑ����x�j�ƉԂ��ꏏ�Ƀ����Y�ɔ[�߂�D�K�n���A���̎��ӂɂ͂������邩��ł͂Ȃ����ƁA�����������Ă��Ƃ���v���܂����B
�@������������G�X�q�x�֑����Ő��ł́A�R�̍D�W�]�͓���������҂��Ă��܂������A�z���ȏ�ɉԂ����炵���A��������܂����B�����x�ƃ��c�o�V�I�K�}�ȂǁA�J����������������܂��G�ɂȂ�悤�Ȍ��i���P�s�b�`�Ő��J��������悤���ґ�ȗŐ��������A�Ԃ̏�Ԃ�V��҂��̂��߂ɔS��A�f�l�̎����ł����Ȃ肢���ʐ^���B�ꂻ���ȋC�����܂����B
�@�Ƃ��ɒJ�ߐs�����`���O���}�̑�Q���������̂͏��߂ĂŁA���̒��ɂ���悤�ł����B�������A�ǂ̉Ԃ�100��������ԂŃp�b�`���ƍ炢�Ă���̂ł��B�\����������������܂��A�i�}�Ō��Ă���̂ɍ����ʐ^�̂悤�c�c�B�R�}�N�T�������Ɍ����̂����߂ĂŁA�u�Q��č炩�Ȃ��A�Ǎ��̉ԂȂ�ł����?�v�ƌ�������A�������u��R�������킢���v�Ɣ������Ďʐ^�ɔ[�߂�ꂽ�̂��A�v���o�̂P�V�[���Ƃ��ĐS�Ɏc��܂��B
�@�G�X�q�x�s�X�g���ł́A�����Łu�������߃X�|�b�g�v�Ƃ��ďЉ��Ă����l�\���r�܂Œ�������Ƒ����̂��܂����B���L�̗Ő���ɂł��������Ȗ~�n��̒n�`�ɁA�r�f�A�A���R�A���A��R�A��A�o�R�����z����āA�G�̂悤�ȏ��F���ł����B�G�X�q�x�́i�K�^�ɂ��H�j�S���R�ɑI��Ă��Ȃ��������A�������o�R������r�I�Â��ŐS�n�悭�A�W�]���Ԃ��y���߂邢���R�Ƃ��āA�����L���O���}�㏸�����R�̈�ɂȂ�܂����B�i�얼�j
|
 |
** |
 |
2013�N8��5���@�@11:31�@�i�B�e�F�얼�j
�^�J�l�V�I�K�}
���������O �@�y���܂̂͂����ȁz�@ |
|
2013�N8��6���@�@5:46�@�i�B�e�F�얼�j
�C���I�E�M
���������� �@�y�܂߉ȁz�@�@ |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@5:53�@�i�B�e�F�얼�j
���c�o�V�I�K�}
�����z��O �@�y���܂̂͂����ȁz |
|
2013�N8��6���@�@5:54�@�i�B�e�F�얼�j
�~���}�_�C�R���\�E
�����z��O �@�y��ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@5:54�@�i�B�e�F�얼�j
�C�u�L�W���R�E�\�E
�����z��O �@�y�����ȁz |
|
2013�N8��6���@�@6:31�@�i�B�e�F�����j
�C���I�g�M��
�����z �@�y���Ƃ��肻���ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@6:31�@�i�B�e�F�����j
�C���M�L���E
�����z �@�y�����傤�ȁz |
|
013�N8��6���@�@6:55�@�i�B�e�F�����j
�~���}�I�_�}�L
�����z�� �@�y����ۂ����ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@6:56�@�i�B�e�F�얼�j
�A�J���m
�����z�� �@�y���ȁz�@ |
|
2013�N�W��6���@�@7:18�@�i�B�e�F�����j
�~���}�_�C�R���\�E
�^���x�ւ̓o��r�� �@�y��ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@8:04�@�i�B�e�F�����j
�n�N�T���V���N�i�Q
�^���x�ւ̓o��r�� �@�y���ȁz |
|
2013�N8��6���@�@7:55�@�i�B�e�F�얼�j
�^�J�l���n�Y�n�n�R
�^���x�ւ̓o��r�� �@�y���ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@8:06�@�i�B�e�F�����j
�n�N�T���C�`�Q
�^���x�ւ̓o��r�� �@�y����ۂ����ȁz |
|
2013�N8��6���@�@7:58�@�i�B�e�F�얼�j
�V�i�m�L���o�C
�^���x�ւ̓o��r�� �@�y����ۂ����ȁz |
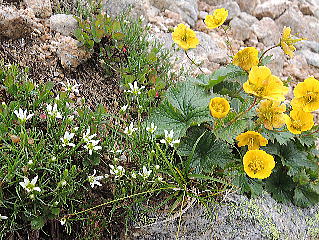 |
|
 |
2013�N8��6���@�@9:53�@�i�B�e�F�얼�j
�C���c���N�T�ƃ~���}�_�C�R���\�E
����ܘY�x�� |
|
2013�N8��6���@�@10:40�@�i�B�e�F�얼�j
�~�Y�X�I�E
�O�c�x��O �@�y���ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@11:14�@�i�B�e�F�얼�j
�C���c���N�T
�O�c�x��O �@�y�Ȃł����ȁz |
|
2013�N8��6���@�@11:41�@�i�B�e�F�얼�j
�R�C���J�K�~
�O�c�x��O�̂��Ԕ��@�y���키�߉ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@11:52�@�i�B�e�F�얼�j
�`���O���}
�O�c�x��O�̂��Ԕ� �@�y��ȁz |
|
2013�N8��6���@�@12:12�@�i�B�e�F�얼�j
�C���M�L���E�ƃC���c���N�T
�O�c�x�� |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@12:22�@�i�B�e�F�얼�j
�R�o�m�R�S���O�T
�O�c�x��@�y���܂̂͂����ȁz |
|
2013�N8��6���@�@12:39�@�i�B�e�F�얼�j
�R�}�N�T
�O�c�x�� �@�y�����ȁz�@ |
 |
|
 |
2013�N8��6���@�@13:42�@�i�B�e�F�얼�j
�c�}�g���\�E
�O�c�x�� �@�y�����ȁz�@ |
|
2013�N8��7���@�@6:46�@�i�B�e�F�얼�j
�A�I�m�c�K�U�N��
�G�X�q�x�� �@�y���ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��7���@�@6:49�@�i�B�e�F�얼�j
�S�[���^�`�o�i
�G�X�q�x�� �@�y�݂����ȁz |
|
2013�N8��7���@�@6:49�@�i�B�e�F�얼�j
�����l�\�E
�G�X�q�x�� �@�y����������ȁz |
 |
|
 |
2013�N8��7���@�@7:29�@�i�B�e�F�����j
�R�C���J�K�~�ƃ`���O���}
�G�X�q�l�\���r |
|
2013�N8��7���@�@8:�P8�@�i�B�e�F�얼�j
�G�]�V�I�K�}
�G�X�q������O �@�y���܂̂͂����ȁz�@ |
 |
|
 |
2013�N8��7���@�@10:03�@�i�B�e�F�얼�j
�z�^���u�N��
�u�i������ �@�y�����傤�ȁz |
|
2013�N8��7���@�@10:04�@�i�B�e�F�얼�j
�Z���W���K���s
�u�i������ �@�y�Ȃł����ȁz |
 |
2013�N8��7���@�@11:04�@�i�B�e�F�얼�j
�\�o�i
�u�i������ �@�y�����傤�ȁz
|
|
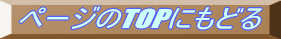
 |
��2012�N7���@�ΑŎR�̉ԂQ�@�����@�떾(���a43�N��)�@�얼�@�^��(���a63�N��)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������������@2012�N10��24�����e
���w�����R�s�x�2012�N7��28�`30���@�j�t����e�R�s�E�����R�`�ΑŎR�c��
�@�@�i�O���j
�@7��30���i���j�@���@�ΑŎR�����������L�����v��։��R�B�A���B
�E�E�E6:20�q���b�e���o�����ΑŎR�Ɍ������܂����B�����n�߂Ă����A���J�r�����̖ؓ������e�̗ѓ��ɃL�k�K�T�\�E�̌����ȌQ��������܂����B�V��̒�̎�O�̑�n�ɂ̓n�N�T���R�U�N���A�A�I�m�c�K�U�N���A�C���C�`���E���ؓ��̗��e�ɌQ���ō炫�ւ茩���ł��B6:50�V��̒�ɓ����B�v�����ȏ�ɍL���A�r������R�U��߂����n�тŁA�r���̎���ɂ͔������^�X�Q�̌Q�������ɗh��A�r���ɉf��ΑŎR�A��k���ڂ�D���܂��B
�V��̒납��ΑŎR�܂ł̗Ő��͐��Ɂu�S��㇗��v�B���C�`���E���܂ł̓C���J�K�~(�W�g)�A�E���o�`�\�E(��)�A�I���^�f(��)�A�q���V���W��(�W��)�A�}���o�_�P�u�L(��)�A�n�N�T���{�E�t�E(��)�A�N���}����(��)�E�E�E�A�F�Ƃ�ǂ�̍��R�̉Ԃ����X�Ɍ���A�ʐ^���B��Ȃ���������o��܂����B�ォ��Ԃɏڂ����얼�����������������Ԃ����������Ă���܂��B
�@���C�`���E�����璸��܂ł́A�J���}�c�\�E(��)�A�E�T�M�L�N(��)�A�V�i�m�L���o�C(��)���o�R���̗��e�ɍ炫�ւ�A�o��̐h����a�炰�܂����B���̍�����K�X���������ߓW�]�������Ȃ�܂����B8:20�ΑŎR��(2,462m)�ɒ����܂����B�c�O�Ȃ���A�ĎR����J���R�ɑ����Ő��̓K�X�̒��ł��B�����̏o�����ɂ͢���C�`���E�������邩���m��Ȃ���ƁA������̉e�Αł܂ōs�����Ƒ��k���Ă��܂������A�W�]�������Ȃ��̂ōs���̂��~�߁A20���̋x�e�㉺�R�J�n�B
�@�o��Ɍ����������Ԃ̎ʐ^���B��Ȃ��������艺��܂����B
�@�i�����j11:00�ɍ�����Ɍ������ĉ��R�J�n�B�x�m����(2,050m)�܂ł͊ɂ₩�ȉ���B��ł͌����Ȃ������T���J���E(��)�A�I�I�o�L�X�~��(��)�A�S�[���^�`�o�i(��)�����e�ɂЂ�����炢�Ă��܂����B
�i�㗪�j�@
���얼����̊��z�i8/30���������[�����甲���j
�@�@���ɂƂ��āA���N�̉ĎR�V�[�Y�����̖{�i�I�ȎR�s�ŁA�����R�̓o�艺��͂��������ł��B�T�E�i�̂悤�ɐ����C�������A���ꂪ�_�ƂȂ��ēW�]���Ղ�A���R�A�����݂�ꂸ�A�C�s�ɋ߂��ł����B�Ƃ͂����A�����炱���̏[����������܂����B�ΑŎR�͈�]���Ă����₩�ȎR�e�ō��R�A���Ɍb�܂�A�ƂĂ��t�H�g�W�F�j�b�N�ł����B���^�X�Q�̍Ő����Əo������̂͏��߂ĂŁA�����A��������Ɠ�l�ŐÂ��Ɍi�F��Ɛ�ł������Ƃ����܂��āA�z���ȏ�̊���������܂����B
��2012�N8��31���@�qe. �j�t����e�R�s�E�����R�`�ΑŎR�c���@�O��@���i���a37�N���j
�@�@�@�@�������������@2012�N8��31���̂g�t�g�`�b���[����蔲��
�@�@�i�O���j
�@�������N���O�A�N���u�c�[���Y���̃c�A�[�Ŗ����R�`�ΑŎR�ɓo�������A���s�̏�����������Ԃ̖��O���������A���ꂩ��Ԃɋ��������悤�ɂȂ�܂����B�w�ǒ�������A�얼���L�q�����ԂƓ����ł����A�����ĕt�����������Ă��������ƁA�@��q��z�ɓo��R���̂킫�ɁA�}�C�Y���\�E�A�I�g�M���\�E�A�L�k�K�T�\�E�Ȃǂ������Ă��炢�܂����B���A�ΑŎR�ɓo��r���ɁA�R�o�C�P�C�\�E�A�n�N�T���`�h���A�N�������Ȃǂ����������Ƃ��o���Ă��܂��B�܂���R�������̂ł����A�w�ǖY��Ă��܂��܂����B�܂��Ԃ�u�˂�R�s�ɂ��������ł��ˁB
|
 |
 |
012�N7��29���@�@16:36�@�i�B�e�F�얼�j
�L�k�K�T�\�E
���J�r �@�y���ȁz |
2012�N7��30���@�@6:50�@�i�B�e�F�얼�j
���^�X�Q
�V��̒� �@�y����肮���ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@7:10�@�i�B�e�F�����j
�I���^�f
���C�`���E�����̓��[ �@�y���ʼnȁz |
2012�N7��30���@�@7:12�@�i�B�e�F�����j
�E���o�`�\�E
���C�`���E�����̓��[ �@�y�䂫�̂����ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@7:13�@�i�B�e�F�����j
�G�]�V�I�K�}
���C�`���E�����̓��[ �@�y���܂̂͂����ȁz�@ |
2012�N7��30���@�@7:13�@�i�B�e�F�����j
�A�L�m�L�����\�E
���C�`���E�����̓��[ �@�y�����ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@7:21�@�i�B�e�F�����j
�I�I�J�T���`
���C�`���E�����̎Ζ� �@�y����ȁz�@ |
2012�N7��30���@�@7:24�@�i�B�e�F�����j
�N���}����
���C�`���E�����̓��[ �@�y���ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@7:25�@�i�B�e�F�����j
�}���o�_�P�u�L
���C�`���E�����̎Ζ� �@�y�����ȁz |
2012�N7��30���@�@7:34�@�i�B�e�F�����j
�~���}�z�c�c�W
���C�`���E����O�̓��[ �@�y���ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@7:36�@�i�B�e�F�����j
�z�\�o�q���V���W��
���C�`���E����O�̓��[ �@�y�����傤�ȁz |
2012�N7��30���@�@7:40�@�i�B�e�F�����j
�~���}�I�_�}�L
���C�`���E����O�̓��[ �@�y����ۂ����ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@7:50�@�i�B�e�F�����j
�V�i�m�L���o�C
���C�`���E����̓��[ �@�y����ۂ����ȁz |
2012�N7��30���@�@7:53�@�i�B�e�F�����j
�J���}�c�\�E
���C�`���E����̓��[ �@�y����ۂ����ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@8:08�@�i�B�e�F�얼�j
�E�T�M�M�N
���C�`���E����̓��[ �@�y�����ȁz |
2012�N7��30���@�@8:59�@�i�B�e�F�����j
�C���J�K�~
�V��̒�`���C�`���E�����̓��[ �@�y���키�߉ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@9:26�@�i�B�e�F�����j
�^�e���}�A�U�~
�V��̒�`���C�`���E�����̓��[ �@�y�����ȁz |
2012�N7��30���@�@10:05�@�i�B�e�F�����j
�n�N�T���`�h��
�V��̒��O�̑�n �@�y���ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@10:09�@�i�B�e�F�����j
�n�N�T���R�U�N��
�V��̒��O�̑�n �@�y�����炻���ȁz |
2012�N7��30���@�@10:10�@�i�B�e�F�����j
�A�I�m�c�K�U�N��
�V��̒��O�̑�n �@�y���ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@11:32�@�i�B�e�F�����j
�T���J���E
�x�m�����߂� �@�y�߂��ȁz |
2012�N7��30���@�@11:33�@�i�B�e�F�����j
�x�j�o�i�C�`�S
�x�m�����߂� �@�y��ȁz |
 |
 |
2012�N7��30���@�@11:35�@�i�B�e�F�����j
�I�I�o�L�X�~��
�x�m�����߂� �@�y���݂�ȁz |
�@2012�N7��30���@�@12:05�@�i�B�e�F�����j
�S�[���^�`�o�i
�x�m�����߂� �@�y�݂����ȁz |
|
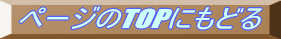
 |
��2012�N7���@�A�|�C�x�̉ԁ@���c�@���u(���a42�N��)�@
�@�@������2012�N8��20�����e
���w�����R�s�x�2012�N7��18�`20���@�j�t����L�u�ɂ��k�C���̃A�|�C�x�o�R�
�@�Q�ƁB�ʐ^�͎B�e�������ɔz�u���܂����B
|
 |
 |
2012�N7��19���@�@7:19
�A�|�C�x�o�R���t��
�N���}���� �@�y���ȁz�@
|
2012�N7��19���@�@8:53
�A�|�C�x�T���ڕt��
�z�\�o�g�E�L �y����ȁz
|
 |
 |
2012�N7��19���@�@9:11
�A�|�C�x�V���ڕt��
�C�u�L�W���R�E�\�E �y���܂̂͂����ȁz
�@�@�@�@�@�@ |
2012�N7��19���@�@9:13
�A�|�C�x�V���ڕt��
�T�}�j�I�g�M���@ �y���Ƃ��肻���ȁz
�@�@�@�@ |

2012�N7��19���@�@9:16
�A�|�C�x�V���ڕt��
�A�|�C�}���e�}�@ �y�Ȃł����ȁz
���邢���z���̉��ł́A�Ԃ��J���Ȃ��@
�@�@�@�@�@ |
 |
|
2012�N7��19���@�@9:21
�A�|�C�x�V���ڕt��
�G�]�m�J�����}�c�o�@�@�y�����ˉȁz�@�@ |
 |
 |
2012�N7��19���@�@9:22�@
�A�|�C�x�V���ڕt��
�L�����o�C�@�y��ȁz
�q���`���}�_���Z�Z���i��Ŋ뜜��̒��j��
�Y�����A���̗c���̓L�����o�C�̗t��H�ׂ�
|
2012�N7��19���@�@9:32
�A�|�C�x�n�̔w�t��
�q���G�]�M�N�@�y�����ȁz |
|
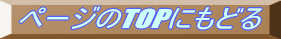
 |
��2012�N7���@�g�����E�V�̉ԁ@�|���@��(���a39�N��)�A���c�@���u(���a42�N��)�@
�@�@������2012�N8��20���A9��2�����e
���w�����R�s�x�2012�N7��13�`18���@�j�t����L�u�ɂ��k�C���E���R�n�o�R�
�@�Q�ƁB�ʐ^�͎B�e�������ɔz�u���܂����B
���V�����{�̃g�����E�V�̋L�^�Ɋւ��Ă͎R�s�̒ʂ�ł��邪�A�傢�ɍ��R�A�������\�����R�s�ł��������B���R���L�̉ԁA�k�A���v�X�Ȃǖ{�B�̍��R�ł��o���ԂȂǎ�ނƗʂ̖L�x���Ɉ��|���ꂽ�B�܂��A�o��ꏊ�̕��͋C�Ȃǂ��̎��R�̑g�ݍ��킹�̖��ɂ������ł������B
���̓��̊�����Љ�����B�Ȃ��A�Ԃ̎��ʂɂ��Ắu�R�k���E���R���R�ώ@�K�C�h�v�ɏ]�����B
��7/14���H�F�J���C�V��̐悩�牄�X�Ƒ����D�^������������A�R�}�h�����ڎw���A�J���C�T���P�i�C��Ɍ����ĉ����Ďb���i�Ƃ���ɐ��ꂪ����A���̎��ӂɂ��Ԕ����L�����Ă��� (9:55�@�@�G�]�R�U�N���A�~���}�L���|�E�Q�A�A�~���}�L���|�E�Q) �B
�R�}�h������l�߁A��ؑт����I�ƃn�C�}�c�т̏�őO�g�����ɏo�Ď��E���J����B���ӂɂ̓C���u�N���Ȃǂ��W�J���Ă����i12�F12�@�B�`�V�}�M�L���E�j�B
�O�g��������P�����̂��鏬�s�[�N�������������r�����U�݂��A����̗����g�����E�V�����B�R�}�h�����ł��������|�����E�R���E�c�M�⑽��ނ̍��R�A�����炫�ւ��Ă����i13�F16�@�C�E�R���E�c�M�A�`���E�m�X�P�\�E�j�B
����L�����v�w��n����[���̃I�v�^�e�V�P�A�\���A��̃r���[�|�C���g�ւ̋A�r�ڂɎ~�܂�(18�F10�@�D����e����̃n�N�T���`�h��)�B
��7/15�@���H�F�e���ꂩ������̃g�����E�V�����������A�H�A���ォ��10���̏��Łi5�F59�@�E���R�r���̃C���u�N���j�B���̐�Łi6�F03�@�F�q���C�\�c�c�W�j�B
�e���g��P�����ē�����牺���ăX�O�Ɂi6�F54�@�G�`���E�m�X�P�\�E�A�G�]�R�U�N���j�A�g�����E�V������O�̓��[�ł�����݂̃R�}�N�T�Ɂi7�F01�@�H�R�}�N�T�j�B�A�r�̃g�����E�V�����ł̓��b�N�����Ԋӏ܃^�C�������i7�F40�@�I�`���E�m�X�P�\�E�A�`�V�}�m�L���o�C�\�E�A�G�]�R�U�N���̉Ԕ��A7�F44�@�J�`���E�m�X�P�\�E�Q���j�B
�O���x�R�}�h����J���C�V��Ɍ����r���̂��Ԕ��Łi10�F29�@�K�R�}�h�����̂��Ԕ��j�B�@
�m2012.09.06�@�|���n
|
 |
 |
2012�N7��14 ���@�@9�F55�@�i�B�e�F�|���j
�R�}�h����Ɍ�������̂��Ԕ�
�@�G�]�R�U�N���@�y�����炻���ȁz�A
�~���}�L���|�E�Q�@�y����ۂ����ȁz |
2012�N7��14 ���@�@9�F55�@�i�B�e�F�|���j
�R�}�h����Ɍ�������̂��Ԕ�
�A�~���}�L���|�E�Q�@�y����ۂ����ȁz |
 |
 |
2012�N7��14 ���@�@12�F12�@�i�B�e�F�|���j
�O�g����
�B�`�V�}�M�L���E�@�y�����傤�ȁz |
2012�N7��14 ���@�@13�F16�@�i�B�e�F�|���j
�g�����E�V����
�C�E�R���E�c�M�@�y����������ȁz�A
�`���E�\�X�P�\�E�@�y��ȁz |
 |
 |
2012�N7��14���@�@14:29�@�i�B�e�F���c�j
����ɂ�
�G�]�q���N���K�^ �@�y���܂̂͂����ȁz |
2012�N7��14 ���@�@18�F10�@�i�B�e�F�|���j
����e���g��
�D�n�N�T���`�h���@�y���ȁz |
 |
 |
2012�N7��15 ���@5�F59�@�i�B�e�F�|���j
���R�r���i�g�����E�V���ォ��10���j
�E�C���u�N���@�y���܂̂͂����ȁz |
2012�N7��15 ���@�@6�F03�@�i�B�e�F�|���j
�g�����E�V���ォ��̋A�r
�F�q���C�\�c�c�W�@�y��މȁz |
 |
 |
2012�N7��15���@�@6:09�@�i�B�e�F���c�j
�g�����E�V���ォ��̋A�r
�C�\�c�c�W �y���ȁz �@
�@�@�@ |
2012�N7�� 15 ���@�@6�F54 �i�B�e�F�|���j
�e���g��P����,����������ăX�O
�G�`���E�m�X�P�\�E�@�y��ȁz�A
�G�]�R�U�N���@�y�����炻���ȁz |
 |
2012�N7��15 ���@�@�V�F01�@�i�B�e�F�|���j
�g�����E�V������O �@�H�R�}�N�T�@�y�����ȁz |
 |
 |
2012�N7��15 ���@�@7�F40�@�i�B�e�F�|���j�@
�g�����E�V����
�I�`���E�\�X�P�\�E�@�y��ȁz�A
�`�V�}�m�L���o�C�\�E�@�y����ۂ����ȁz�A
�G�]�R�U�N���@�y�����炻���ȁz�̂��Ԕ� |
2012�N7��15 ���@�@7�F44�@�i�B�e�F�|���j�@
�g�����E�V����
�J�`���E�\�X�P�\�E�@�y��ȁz�@�Q�� |
 |
 |
2012�N7��15���@�@8:41�@�i�B�e�F���c�j�@
�O�g����
�`�V�}�L�����C�J�i�^�J�l�I�~�i�G�V�j
�y���݂Ȃ����ȁz |
2012�N7��15 ���@�@10�F29�@�i�B�e�F�|���j
�K�R�}�h�����̂��Ԕ� |
|
|
|
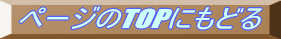
 |
��2010�N10�`11���@�q�}�����̉ԁi���̂Q�j�@���c�@���u(���a42�N��)�@
�@�@������2011�N2��3�����e
�@�@10��21������11��11���A�N�[���u�E�q�}�[���g���b�L���O�ɂł����܂����B
�@�@�i�ڍׂ́w�j�t������121���x�Ɍf�ڗ\��ł��j
�@�@�g���b�L���O���Ɍ����ԁX���A��N���e�����q�}�����̉Ԃ̑��҂Ƃ��ē��e���܂��B
|
 |
 |
 |
2010.10.30�@13:38
Lobche�t��
���I���g�|�f�B�E���E���m�P�t�@����Leontopodiumu�@monocephalum
�i�L�N�ȃE�X���L�\�E���j |
2010.10.�@9:53
Phungi�@Thanga�t��
���I���g�|�f�B�E���E�q�}�����k���@Leontopodium�@Himalayaneu
�i�L�N�ȃE�X���L�\�E���j |
2010.10.26�@8:50
Sanasa�t��
�L�A�i���g�D�X�E���o�g�D�X�@Cyananthus�@lobatus
�i�L�L���E�ȃL�A�i���g�D�X�� |
 |
 |
 |
2010.10.30�@14:10
Lobche�t��
�q�b�|���e�B�A�E�S�b�V�s�i�H�@Hippolytia�@gossypina
�i�L�N�ȃq�b�|���e�B�A���j |
2010.11.03�@8:29
Lusa�t��
�q���V�������g�E�i���j
Cotoneaster�@microphyllus
�i�o���ȁj |
2010.11.03�@8:11
Lusa�t��
�H���^�X�Q�̂悤�ȉԁH��
�������B
���O���������������B |
�u�q�}�����A����}�Ӂv�i�g�c�@�O�i�v���@�R�ƌk�J�Ёj����
�@�ʐ^�B�e�F�����@�떾(���a43�N��)
|
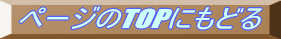
 |
��2010�N8���@���������̉ԁ@�����@�떾(���a43�N��)�@�얼�@�^��(���a62�N��)
�@�@������2010�N9��10�����e
���w�����R�s�x�2010�N8��12�`17���@���������R�s�@�Q��
�@�@����B�����Ԃ̎�ނ͑����A���肵�������ł�31��ł����A�Ԃ̏�Ԃ��ǂ��Ȃ��̂������܂����B�ʐ^�͎B�e�������ɔz�u���܂����B
���_�m�����ӂ͉Ԃ̖����ł����A�W�����{�Ȃ̂ʼnẲԂ͏I����Ă���Ɗ��҂��Ă��܂���ł����B�Ă̒�A�_�m���̃A���X�J�뉀�ł̓`���O���}�̌Q���͍炫�I����Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�A���v�X�뉀�i�c��x�j�ɍs���ƁA�`���O���}�A�V�i�m�L���o�C�A�n�N�T���C�`�Q�̌Q���������ɍ炫�ւ��Ă��܂����B����ɗ����A���V�������ۏ�z�܂ł̊�ۏ��J�����̓����N���}�����A�~���}�g���J�u�g�A�E�T�M�M�N�A�V�i�m�L���o�C�A�n�N�T���C�`�Q�A���c�o�V�I�K�}������ɍ炢�Ă��܂����B��ۏ�z�`���������`�o�Z�����̓����~���}�L���|�E�Q�A�E�T�M�L�N�A�R�C���J�K�~�A�A�I�m�c�K�U�N���Ȃǐ^������ł����B�o�Z��������|�܊x�ւ̗Ő��ł��R�o�C�P�C�\�E�A�n�N�T���t�E���A�C���J�K�~�Ȃǂ��y���݂܂����B�S�c�肾�����̂͗\�肵�čs���Ȃ������Ԗؑ�A�ܘY��A�c����̌����A�����ܘY�x�̃J�[���̉Ԃł��B�������������ȉԁX�ɏo������Ƃł��傤�B�i�����D�얼�j
|
 |
 |
2010�N8��13���@�@13:01�@�i�B�e�F�����j
��t���ւ̓r���ɂ�
�S�[���^�`�o�i �@�y�~�Y�L�ȁz |
2010�N8��13���@�@13:14�@�i�B�e�F�����j
��t���ւ̓r���ɂ�
�I���^�f�@ �y�^�f�ȁz |

2010�N8��13���@�@13:17�@�i�B�e�G�����j
��t���ւ̓r���ɂ�
�~���}�V�V�E�h�@ �y�Z���ȁz |

2010�N8��13���@�@13:21�@�i�B�e�F�얼�j
��t���ւ̓r���ɂ�
�G�]�V�I�K�}�@ �y�S�}�m�n�O�T�ȁz

2010�N8��14���@�@9:24 �i�B�e�F�얼�j
�c��x����
�`���O���}�@ �y�o���ȁz |
 |
 |
2010�N8��14���@�@9:48 (�B�e�F�얼)
�c��x����
�C���C�`���E�@ �y�L�N�ȁz |
2010�N8��14���@�@11:20 (�B�e�F�얼)
�_�m���i�R���i�ϑ����t�߁j
�A�I�m�c�K�U�N���@ �y�c�c�W�ȁz |
 |
 |
2010�N8��14���@�@11:31�@�i�B�e�F�����j
�_�m�� �i�R���i�ϑ����t�߁j
�~���}�A�L�m�L�����\�E�@ �y�L�N�ȁz |
2010�N8��14���@�@11:34�@�i�B�e�F�얼�j
�_�m���i�R���i�ϑ����t�߁j
���}�n�n�R�@ �y�L�N�ȁz |
 |
 |
2010�N8��15���@�@8:11�@�i�B�e�F�����j
��ۏ�z�ւ̓r��
�~���}�g���J�u�g�@ �y�L���|�E�Q�ȁz |
2010�N8��15���@�@8:25�@�i�B�e�F�����j
��ۏ�z�ւ̓r��
�V�i�m�L���o�C�@ �y�L���|�E�Q�ȁz |
 |
 |
2010�N8��15���@�@8:38�@�i�B�e�F�����j
��ۏ�z�ւ̓r��
�E�T�M�L�N�@ �y�L�N�ȁz |
2010�N8��15���@�@9:08�@�i�B�e�F�����j
��ۏ�z��O
�~���}�L���|�E�Q�@ �y�L���|�E�Q�ȁz |
 |
 |
2010�N8��15���@�@9:11�@�i�B�e�F�����j
��ۏ�z��O
���c�o�V�I�K�}�@ �y�S�}�m�n�O�T�ȁz |
2010�N8��15���@�@9:11�@�i�B�e�F�얼�j
��ۏ�z��O
�n�N�T���C�`�Q�@ �y�L���|�E�Q�ȁz |

2010�N8��15���@�@10:07�@�i�B�e�F�����j
��ۏ�z�ւ̓r��
�N���}�����@ �y�����ȁz

2010�N8��15���@�@13:40�@�i�B�e�F�����j
�o�Z�����ւ̓r��
�R�C���J�K�~�@ �y�C���E���ȁz |

2010�N8��15���@�@10:12�@�i�B�e�F�����j
���������ւ̓r��
�I�^�J���R�E�@ �y�����ȁz |

2010�N8��15���@�@10:17�@�i�B�e�F�����j
���������ւ̓r��
�R�o�C�P�C�\�E�@ �y�����ȁz |

2010�N8��16���@�@6:59�@�i�B�e�F�����j
��������ւ̓r��
�^�J�l���n�Y�n�n�R�@ �y�L�N�ȁz

2010�N8��16���@�@7:34�@�i�B�e�F�����j
���������O
�n�N�T���t�E���@ �y�t�E���\�E�ȁz |

�@2010�N8��16���@�@7:25�@(�B�e�F����)
���������O
�V���c�P�\�E�@ �y�o���ȁz |

2010�N8��16���@�@7:37�@�i�B�e�F�����j
�|�܊x�ւ̓r��
�C���J�K�~�@ �y�C���E���ȁz |
|
|
|
|
|
|
|
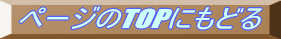
 |
|
��2010�N7���@�ΑŎR�̉ԁ@�R�{�@�����@(���a36�N��)
�@�@�@���������������������@2010�N8��29�����e
|
 |
 |
2010�N�V��23���@7:07
�ΑŎR���V��m��
�n�N�T���R�U�N���@�y�T�N���\�E�ȁz |
2010�N�V��23���@7:08
�ΑŎR���V��m��
���^�X�Q�@�y�J���c���O�T�ȁz |
|
| ���V�O���z�����O�g�̘V�v�w�̉Ԍ��B���N�͐ϐႪ�����A�Q�������Ȃ��B |
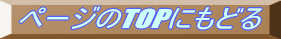
 |
��2010�N7���@���A��̉ԁi�P�F���x�j�@�����@�떾(���a43�N��)
�@�@������2010�N8��8�����e
�w�����R�s�x�2010�N7��8�`14���@���A��c���i���x�`�g�����E�V�R�j�Q��
�Ԃ̔z�u�͍s����̏o�(�B�e����)���ł��B�����Ԃ��d�����Čf�ڂ��Ă��܂��B
�Ԃ̖��O�́w�k�C���̍��R�A���x�i�k�C���V���Ёj�̂��̂��̗p���܂����B |
 |
 |
2010�N7��8���@15:24
���x�ւ̓r���ɂ�
�E�R���E�c�M �@�y�X�C�J�Y���ȁz |
2009�N7��8���@15:58
���x�ւ̓r���ɂ�
�`�V�}�m�L���o�C�\�E �y�L���|�E�Q�ȁz |
 |
 |
2009�N7��8���@16:01
���x�ւ̓r���ɂ�
�@�@�I�I�J�T���` �y�Z���ȁz |
2009�N7��8���@16:03
���x�ւ̓r���ɂ�
�@�n�N�T���`�h�� �y�����ȁz |
 |
 |
2009�N7��8���@16:05
���x�ւ̓r���ɂ�
�@�g�J�`�t�E�� �y�t�E���\�E�ȁz |
2009�N7��8���@16:14
���x�R���t��
�@�G�]�c�c�W �y�c�c�W�ȁz |
 |
 |
2009�N7��8���@16:16
���x�R���t��
�@�C���u�N�� �y�S�}�m�n�O�T�ȁz |
2009�N7��8���@16:36
���x�Ύ��t��
�@�G�]�R�U�N�� �y�T�N���\�E�ȁz |
 |
|
2009�N7��8���@16:37
���x�Ύ��t��
�@�`���O���} �y�o���ȁz |
|
|
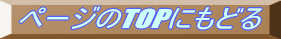
 |
��2010�N7���@���A��̉ԁi�Q�F�k�C�x�E���_�x�E����x�j�@�����@�떾(���a43�N��)
�@�@������2010�N8��8�����e
�w�����R�s�x�2010�N7��8�`14���@���A��c���i���x�`�g�����E�V�R�j�Q��
�Ԃ̔z�u�͍s����̏o�(�B�e����)���ł��B�����Ԃ��d�����Čf�ڂ��Ă��܂��B
�Ԃ̖��O�́w�k�C���̍��R�A���x�i�k�C���V���Ёj�̂��̂��̗p���܂����B
|
 |
 |
2009�N7��9���@ 5:38
�k�C�x�̓r���ɂ�
�C���u�N���̌Q���@�@�y�S�}�m�n�O�T�ȁz |
2009�N7��9���@ 5:42
�k�C�x�̓r���ɂ�
�@�E���W���i�i�J�}�h�@�@�y�o���ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@ 6:10
�k�C�x�̓r���ɂ�
�N���}���L�m�V�^�@�@�y���L�m�V�^�ȁz |
2009�N7��9���@6:14
�k�C�x�̓r���ɂ�
�z�\�o�c���N�T�@�@�@�y�i�i�f�V�R�ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@6:35
�k�C�x�̓r���ɂ�
�C���q�Q�̌Q���@�@�@�y�c�c�W�ȁz |
2009�N7��9���@ 6:52
�k�C�x�R���t��
�L�o�i�V�I�K�}�@�@�y�S�}�m�n�O�T�ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@ 7:00
���_����̓r���ɂ�
�n�N�T���`�h���@�@�@�y�����ȁz |
2009�N7��9���@ 7:18
�k�C����̓r���ɂ�
�R�}�N�T�@�@�y�P�V�ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@ 7:19
���_����̓r���ɂ�
�G�]�m�I���}ɃG���h�E�@�@�y�}���ȁz |
2009�N7��9���@ 7:37
���_����̓r���ɂ�
�G�]�m�n�N�T���C�`�Qށ@�@�y�L���|�E�Q�ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@ 9:3
���_���ɂ�
�G�]�n�n�R�����M�@�@�y�L�N�ȁz |
2009�N7��9���@ 11:54
�Ő�����ւ̓r���ɂ�
�G�]�c�c�Wށ@�@�y�c�c�W�ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@ 12:32
����x�ւ̓r���ɂ�
�@�z�\�o�c���N�T�@�@�@�y�i�f�V�R�ȁz |
2009�N7��9���@ 12:39
����x�ւ̓r���ɂ�
�`�V�}�L�����C�J�@�@�@�y�I�~�i�G�V�ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@ 12:48
����x�̓r���ɂ�
�R�}�N�T�@�@�y�P�V�ȁz |
�@2009�N7��9���@ 12:50
����x�̓r���ɂ�
�@�}���o�V���c�P�@�@�y�o���ȁz |
 |
 |
2009�N7��9���@ 13:01
����x�̓r���ɂ�
�@�V���o�i�~���}�A�Y�}�M�Nށ@�@�y�L�N�ȁz |
2009�N7��9���@ 13:01
����x�̓r���ɂ�
�z�\�o�E���b�v�\�E�@�@�y�E���b�v�\�E�ȁz |
 |
|
2009�N7��9���@ 13:06
����x�̓r���ɂ�
���A�J���L���o�C�@�@�y�o���@�ȁz |
|
|
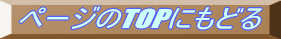

|
��2010�N7���@���A��̉ԁi�R�F�����P���E���ʊx�j�@�����@�떾(���a43�N��)
�@�@������2010�N8��8�����e
�w�����R�s�x�2010�N7��8�`14���@���A��c���i���x�`�g�����E�V�R�j�Q��
�Ԃ̔z�u�͍s����̏o�(�B�e����)���ł��B�����Ԃ��d�����Čf�ڂ��Ă��܂��B
�Ԃ̖��O�́w�k�C���̍��R�A���x�i�k�C���V���Ёj�̂��̂��̗p���܂����B
|
�@�@�@
 |
 |
2009�N7��10���@ 5:26
�����P���ɂ�
�`�V�}�L�����C�J�A�G�]�c�c�W�A
�C���u�N���A�G�]�n�n�R�����M |
2009�N7��10���@ 5:29
�����P���ɂ�
�G�]�c�c�W�@�@�y�c�c�W�ȁz
�@�@�@ |
 |
 |
2009�N7��10���@ 5:36
�����P���ɂ�
�`�V�}�M�L���E�@�@�y�L�L���E�ȁz |
2009�N7��10���@ 5:37
�����P���ɂ�
�G�]�n�n�R�����M�̌Q���@�@�y�L�N�ȁz |
 |
 |
2009�N7��10���@ 5:38
�����P���ɂ�
�S�[���^�`�o�i�@�@�y�~�Y�L�ȁz |
2009�N7��10���@ 6:31
�����P���ɂ�
�R�}�N�T�@�@�y�P�V�ȁz
|
 |
 |
2009�N7��10���@ 6:42
�����P���ɂ�
���c�o�V�I�K�}�@�@�y�S�}�m�n�O�T�ȁz |
2009�N7��10���@ 8:07
�����P���ɂ�
�C���u�N���@�@�y�S�}�m�n�O�T�ȁz |

2009�N7��10���@ 5:31
���ʊx�̓r���ɂ�
�`���O���}�̑�Q���@�@�y�o���ȁz |
 |
|
2009�N7��10���@ 10:43
���ʊx��������t��
�~���}�I�O���}�@�@�@�y�L�N�ȁz |
|
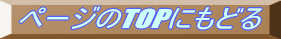
 |
��2010�N7���@���A��̉ԁi�S�F���_�x�E�g�����E�V�R�j�@�����@�떾(���a43�N��)
�@�@������2010�N8��8�����e
�w�����R�s�x�2010�N7��8�`14���@���A��c���i���x�`�g�����E�V�R�j�Q��
�Ԃ̔z�u�͍s����̏o�(�B�e����)���ł��B�����Ԃ��d�����Čf�ڂ��Ă��܂��B
�Ԃ̖��O�́w�k�C���̍��R�A���x�i�k�C���V���Ёj�̂��̂��̗p���܂����B
|
 |

2009�N7��11���@ 7:24
���_���̓r���ɂ�
�G�]�R�U�N���@�@�y�T�N���\�E�ȁz |
2009�N7��11���@ 7:10
���_���̓r���ɂ�
�@�@�@�E���W���i�i�J�}�h�@�@�y�o���ȁz�@�@�@ |
�@�@�@�@ |
 |
 |
2009�N7��11���@ 7:26
���_���̓r���ɂ�
�G�]�m�n�N�T���C�`�Q�̌Q���y�L���|�E�Q�ȁz |
2009�N7��11���@ 7:34
���_���ɂ�
�`���O���}�@�@�@�y�o���ȁz |
 |
 |
2009�N7��11���@ 7:37
���_���ɂ�
�z�\�o�E���b�v�\�E�y�E���b�v�\�E�ȁz
|
2009�N7��11���@ 7:39
���_���ɂ�
�z�\�o�E���b�v�\�E�ƃ`���O���} |
 |
 |
2009�N7��11���@ 8:01
���_���ɂ�
�G�]�m�n�N�T���C�`�Q�ƃz�\�o�E���b�v�\�E |
2009�N7��11���@ 8:14
���_�x�̓r���ɂ�
�L�o�i�V���N�i�Q�̌Q���y�c�c�W�ȁz |
 |
|
2009�N7��11���@ 8:14
���_�x�̓r���ɂ�
�`���O���}�̌��n������̑�Q���y�o���ȁz |
|
 |
 |
2009�N7��13���@ 7:22
�g�����E�V�R�̓r���ɂ�
�G�]�m�c�K�U�N���@�@�@�y�c�c�W�ȁz |
2009�N7��13���@ 9:51
�O�g�����ɂ�
�`�V�}�M�L���E�@�@�y�L�L���E�ȁz |
|
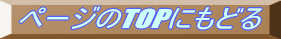
 |
��2010�N6���@�U���̏㍂�n�̉ԁ@�����@�M���i���a38�N���j�@�@������2010�N6��9�����e
���摜���N���b�N����Ɖ摜���傫���\������܂��B |
|
|
�Y�~�i�o���ȃ����S���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�������͓̉����߂��̔�r�I�����Y�~�̖̉Ԃ̂ڂ݁B�Q�̂����́A�Ԃ��F��ттĂ��邪�A�J�Ԃ���Ɣ����Ȃ�B���̖́A�ږ̑�Ƃ��ė��p�����B�㍂�n�ł́A�����ƌĂ�邪�A�R�����S�Ƃ����n��������B�Ⴂ�͂܂��Q�����������̂悤�ŐԂ��F�������Ȃ����̂����������B
|
|
|
�V���o�i�m�G�����C�\�E�i�����ȃG�����C�\�E���j�@�@
�@�鍑�z�e���̓����̓��[�ɂ���B�߂��Ɏ��F�̉Ԃ̃G�����C�\�E������B |
|
|
�I�I�J���m�L�i�X�C�J�Y���ȃK�}�Y�~���j�@�@�@�@�@�@�@
�@�c�㎼���̘H�T�ɂ������B�㍂�n�ł͂�����Ƃ���ŏo����Ƃ��ł���B����x�̔��E�q���̐�k�̖��[�̏��ɂ��P�O���[�g�����y��̏�ɂ������B�t���傫�ȋT�̍b�̌`�����Ă���̂Ŗ��Â���ꂽ�B�t�����ɐH����̂Ń��V�J���Ƃ������B |
|
|
�n�V���h�R���i�i�X�ȃn�V���h�R�����j�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�c�㎼�����ł��Ƃ���̗ѓ��̉����ƂȂ��Ă����B�n���s�ɖғł�����A�H�ׂ�ƌ��o�Ǐ���N����������Ƃ��납�炱�̖����t����ꂽ�B�n���s�͒��ɍ܁E�ۖ�Ƃ��Ă�����B�V�[�{���g�̓��{�؍ݒ��Ƀn�V���h�R���Ɋւ����b������B�i���J���Z�̎ʐ��}�E�}�L�V���r�b�`�̖����E�u��i����^�v�E�V�[�{���g�̊Ӓ�Ⴂ�ɂ��U����Ƃ��Ă̌��\�̔����E�y�����ד��X�j
|
|
|
�N���}�o�c�N�o�l�\�E�i�����ȃc�N�o�l�\�E���j�@�@�@�@�@
�@�c�㎼������c�㋴�������H�T�ł݂�B�t��6�`8�����Ă��āA�H���˂��̉H�Ɏ��Ă���̂ł��̖��������B
|
|
|
���V���E�����J�Y���i�V�\�ȃ��V���E�����J�Y�����j�@�@�@�@
�@�\�̋Ȗځu������v�̒��ŁC�n�Ӎj���S���̘r���b������B���̐�ꂽ�r�ɂ��̉Ԃ����Ă���̂Ń��V���E�����J�Y���Ɩ��Â���ꂽ�Ƃ����B�c�㎼������c�㋴�������H�T�Ō������B���̐��b�����������̂ɁA�̕��ꕑ�x��߂苴����أ�A���S��j�٣������B
|
|
|
�E���~�Y�U�N���i�o���ȃT�N�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�㍂�n�o�X�^�[�~�i������鍑�z�e���������ؓ�����݂����B�T�N�������Ԃ��\���C���V�m�i�U�`��j�I�I�V�}�U�N��(�U�[��)���Ƃ͂��ƂȂ�A����ԏ��i���̂悤�ȉԂ̂������j�ƂȂ��Ă���B�܂��Q�̏�Ԃł���B�ԁE���i�̍��j�E���i�Ԃ��������ځj�����Ђ���Ē��Ђ��ɂ���B5�����{�ɔ��n���ł��̉Ԃ��炢�Ă������A�㍂�n�͊C��1500���[�g���Ŋ�������6���͂��߂ł��Q�ł���B |
|
|
�l�R�m���\�E�i���L�m�V�^�ȃl�R�m���\�E���j�@�@�@�@�@�@�@�@
�@6��5����5���ɋN���Ċx��������֎U��B�x��o�R���߂��̉����̎���ɔ��������B���قɋA���Ď��͂�������痠��̏����ȗ���̖T�ɒ���1���[�g����40�Z���`���炢�̌Q��������A���̂Ȃ��ɂ�������ƃl�R�m���\�E���l�܂��Ă����B
|
|
|
�A�}�h�R���i�����ȃA�}�h�R�����j�@�@�@�@�@�@
�@���쉈���̓��Ŋ��J�R���H�T�ł݂����B�������܂Ƃ܂��Ă����B�t�̘e����ԕ�����{�o���Ă�����̂Ɗ�œ�ɕ�����ē�{�ƂȂ��Ă�����̂�����B |
| **** |
|
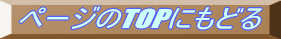

|
|
��2009�N10�`11���@�q�}�����̉ԁ@���c�@���u(���a42�N��)�@������2009�N12��23�����e
10��������11�����߂ɂ����ăq�}�����g���b�L���O�ɂł������B
����Ȏ����Ȃ̂ɁA�l�p�[���͎v���Ă�����肸���Ƃ����ƒg���������B
����ł��A�R�C�O�O�O���t�߂ł́A���͒��F�Ɍ͂�Ă����B�z���܂��T���ƁA����܂�����A�Ԃ��B���ɂ́A�h���C�t�����[���������̂�����܂����c�B
�Ԃ̖��O�ɂ��ẮA�������̒��ԂƂ������x�����킩��܂���B��������ׂ������߂悤�ƍl���Ă��܂����A�������Ă�����������肪�����ł��B
|
 |
 |
 |
2009�N10��30���@
Syangboche�̋u�ɂ�
Gentiana�@Depressa�@
�����h�E�̒��� |
2009�N10��30���@
Syangboche�̋u�ɂ�
������ |
2009�N10��30���@
Syangboche�̋u�ɂ�
���}�n�n�R�̒��� |
 |
 |
 |
2009�N10��30���@
�G�x���X�g�r���[�z�e���t�߂�
�E�X���L�\�E�̒��� |
2009�N10��31���@
Syanboche�̃w���|�[�g�t�߂�
�f���������������@micans�@
�����h�E�̒��� |
2009�N10��30��
�G�x���X�g�r���[�z�e���t�߂�
�i�n�ꎁ�B�e�j
�f���������������@micans�@
�����h�E�̒��� |
 |
 |
 |
2009�N10��30��
�G�x���X�g�r���[�z�e���t�߂�
�i�n�ꎁ�B�e�j
�E�X���L�\�E�̒��� |
2009�N11��3��
�Z�R���Εt�߁i�_�E���M���R�[�j
�C���C���`���̒��� |
2009�N11��3��
�Z�R���Εt�߁i�_�E���M���R�[�j
�A�X�^�[�̒��� |
|
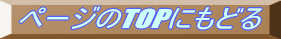

*** |
��2009�N8���@���R�̉ԁ@�|���@��(���a39�N��)�@�@�@������2009�N9��24�����e
�w�����R�s�x�2009�N8��26�`29���@�Ă̏I���ɉ���̔��R�ɏo�|���܂����B��Q��
�@�����̗��E���R�͍��R�A���̓_�ł��V���ɖ��������Y�n�̖��R�ŁA�u�n�N�T���v�̖���������A�������ł���ςɑ����A�ƂĂ��{�e�ł͏Љ��Ȃ��B���ꂾ���ɉԂ̍Ő����ɂ͖K���l�������A���ǂ����������@�@�����V���Ёw���{�S���R�@���R
�r���x ��R�x��� |
 |
 |
2009�N8��27���@10:57 ���я���
�n�N�T���V���W�� |
2009�N8��27���@11:43 ���h�V��
���}�A�W�T�C�i�I�I�J҃m�L�������j |
 |
 |
2009�N8��27���@12:22 �r�V�������߂��ɂ�
�~���}�g���J�u�g�ƃI�j�V���c�P |
2009�N8��27���@12:22 �엳����`���{�R��̊�
�~���}�g���J�u�g |
 |
 |
2009�N8��27���@13:36 �엳����`���{�R��̊�
�n�N�T���t�E�� |
2009�N8��27�� 13:36
���������O��Ɍ������r�� �@�@�@�C���M�L���E |
 |
 |
2009�N8��27���@16:47�@�����ɂ�
�~���}�A�L�m�L�����\�E�ƃn�N�T���t�E�� |
2009�N8��28���@8:13�@�G�R�[���C���ɂ�
�`���O���}�̉Ԓ��i���̂�����Q�������j |
 |
 |
2009�N8��28���@8:19�@�G�R�[���C���ɂ�
�J���C�g�\�E |
2009�N8��28���@8:36�@
�G�R�[���C���A�엳����㕔�@�@�@�@�@�V���c�P�\�E |
 |
 |
2009�N8��28���@8:36
�G�R�[���C���A�엳���@�@�E�X���L�\�E�̓��� |
2009�N8��28���@9:03�@�@�@�엳���ɂ�
�C�u�L�g���m�I�A�~���}�n�N�T���g���J�u�g�A
�n�N�T���{�E�t�E |
 |
 |
2009�N8��28���@10:16���h�V�������ɂ�
�Z���W���K���s |
2009�N8��28���@11:36
�ʓ��o���݂̒苴�߂��ɂā@�@�T���V�i�V���E�} |
�@�@�@�@
|
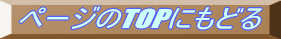

*** |
��2009�N7���@Meconopsis in Bhutan�@�����@��(���a33�N��)�@�@�@������2009�N8���V����P�M
7�����Ɏ��̗F�l�i�ꋴOB)���u�[�^���ɏo�����A�Y�t�̑f���炵�����C���J���[��Meconopsis�̉Ԃ��B�e���Ă��܂����B�@�s������͊O���l�ɏ��߂ĊJ�����ꂽ�n��̗R�ŁA�f�l�ڂɂ̓S�[�W���X�őN��A�܂��쐶���ӂ��f���炵���F�ʂɋ����Ă��܂��B�@�u�[�Q���r���A�̂悤�ȐF�ł��ˁB�@�����ւ����ƕ����܂����B �C�O����̔����͗\�z�O�ɂ��������Ă��܂��B
������2009�N9��9����2�M
�B�e�ҁF�@���M�Y�i�ꋴ�呲�j�@���f�R��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��������A����͖�100���ŋ���A�_�ˑ�A���k�傪�����j
�B�e���F�@2009�N7�����{
��@ ���F�@�u�[�^��
�w�@ ���F�@Meconopsis wallichii
����قǑN�₩�ȃ��C���J���[��Meconopsis�͒������A�u�[�^�������̂悤�ł��B�@�C�O����̔����͂�������܂����AChris Bonington����̃��[�����������L�Љ�܂��B
Hi Tom,
What beautiful flowers, superbly photographed ? I have never been to Bhutan. I really must go.
Chris
On 5/8/09 02:12, "Tamotsu Nakamura" <t-naka@est.hi-ho.ne.jp> wrote:
Dear Friends,
Presumably you would be enjoying nice summer holidays.
I send you herewith rare and marvelously beautiful flowers "wine-color Meconopsis" in Bhutan, as attached. A friend of mine took the pictures during a flower trekking tour (late July) having entered the region first opened to foreigners.
All good wishes,
Tom Nakamura
|
*** |
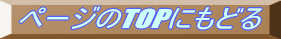
 |
��2009�N8���@�J���C�G�N�E�`�J�E�V�R�̉ԁ@�얼�@�^���@(���a62�N��)������2009�N8��24�����e
|
| �����ׂĂW���W���ɔ��m��J�[���ŎB�e�B���̂悤�ɐ�k�͂킸���ł����A�Q���O�܂ł͂��Ȃ�L���c���Ă��������ł��B�Ⴊ���������肾����ł��傤���B���������ɉԂ��炫���낢�A�����ł����B |
 |
 |
| 2009�N8��8���@8:56�@�@�^�J�l�O���i�C�t�E�� |
2009�N8��8���@8:58:�@�@�~���}�L���|�E�Q |
 |
 |
| 2009�N8��8���@9:47�@�@�@�V�i�m�L���o�C |
2009�N8��8���@10:50�@�@�G�]�c�c�W |
 |
|
| 2009�N8��8���@12:41�@�@�`���O���} |
�@ |
|
�y���Ƃ����z
���̂ق��A�J�[���₻�̑O��ŏ��Ȃ��Ƃ����̂悤�ȉԁX�����܂����B
�@���j�S�[���^�`�o�i
�@���j�E�T�M�M�N�A�j�b�R�E�L�X�Q
�@�j�^�e���}�����h�E�A�~���}�N���K�^
�@���j�C���u�N��
�@�s���N�j���c�o�V�I�K�} |
��2007�N�V���@�k�C���̉ԁi���K�x�E�當���E�r���R�j�@�g��@���v(���a39�N��)
�@�@�@�@�@������2009�N9��4�����e
2007�N�k�C���̉Ԃ̗�
7����4������12���܂ŁA�當���A���K�x�A�r���R�ʼnԂ̎R�����y���݂܂����B�Q���҂́A���㋱(S31)�E�ێR����(S33)�E�g�엲�v(S39)�I���q�v�ȁE�{�ԍ_(S39)�E�����a�l(S40)�E�����v��(S41)�̂V���B
70��ނ��鑐�̉Ԃ��ώ@���A���コ��A�ێR����A����ɊێR����̗F�l�ō��R�A���ɏڂ����e���̂��O���̔M�ӂŁA���̎햼��ł��܂����B�܂��A���������̉̍˃u�i��(���{�̃u�i�̖k��)��T�K���܂����B���̎R���́A�w�j�t�����x��110���́u�k�C���E
�ԂƎR�̗��v(�����v��)�ɏڂ����ڂ��Ă��܂��B
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������N���b�N����Ɠ��Y�L����PDF�ł������ɂȂ�܂��B
|
 |
�@ |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@�@���K�x�̂��Ԕ�
�`�V�}�t�E���A���}�u�L�V���E�}�A�C�u�L�g���m�I�A
���u���V�I�K�}�A�G�]�J���]�E�A�~���}�L���|�E�Q
�ȂǁB |
�@200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�@�當��
�@�q�I�E�M�A�����@�y�A�����ȁz
�@�t�̕t�������A�w��Ɏ��Ă��邱�Ƃ���
�@���t����ꂽ�B�@[�}�Ӈ@] |
 |
 |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�n�C�I�g�M���@�y�I�g�M���\�E�ȁz
�I�g�M���́A��B��̏���̔閧��R�炵��
����Z���a��E�����Ƃ����`���Ɋ�Â��B[�}�ӇB] |
�@200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�當��
�@�G�]�E�X���L�\�E (���u���E�X���L�\�E)�@�y�L�N�ȁz
�@�當���ɑ����B���R�̃E�X���L�\�E�́A
�@�ЂƂ̎R�ɂP��ނ��������Ă��Ȃ����̂������B
�@����ŁA�悭�n�����擪�ɕt�������O�ƂȂ�B
�@�@[�}�Ӈ@] |
 |
 |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�G�]�m�`�`�S�O�T�@�y�L�N�ȁz
���������n�ɐ�����A���Y�َ�̑��N���B
�@[�}�Ӈ@]�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�@200�V�N7��11���@�B�e�F����@�@�@�r���R
�@�~���}�I�_�}�L�@�y�L���|�E�Q�ȁz
�@�I�_�}�L�́A���i�@�D��Ɏg���������j�ŁA
�@�Ԃ̌`����A�z�������́B�@�@[�}�ӇC] |
 |
 |
200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�當��
�~���}�L���|�E�Q�@�y�L���|�E�Q�ȁz
�L���|�E�Q�́A���n�̃E�}�m�A�V�K�^�̕ʖ��B
�@[�}�Ӈ@]�@ |
�@200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�當��
�@���u���L���o�C�\�E�@�y�L���|�E�Q�ȁz
�@�Ԗ��́A�當���ō炭�A���F�̔~�Ɏ�����
�@�ƌ������Ƃŕt����ꂽ�B�@�m�C���^�[�l�b�g����n |
 |
 |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�J���}�c�\�E�@�y�L���|�E�Q�ȁz
�Ԃ̌`���A���̃J���}�c�̗t�Ɍ����Ă�
�i�J���}�c�́A�t�����G�ɕ`���ꂽ���Ɏ���
���邽�߁j�B�@ [�C���^�[�l�b�g����] |
�@200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@ ���K�x
�@�G�]�m�n�N�T���C�`�Q�@�y�L���|�E�Q�ȁz
�@�����ԕق̂悤�Ɍ�����̂́A�ӕЁB
�@�{�B�̃n�N�T���C�`�Q�Ɣ�ׂ�ƁA�t�̐悪
�@����قǐ��Ȃ��B�@ |
 |
 |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
���Ԕ��i�G�]�m�n�N�T���C�`�Q�j
|
�@200�V�N7��9���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K���z�e��
�@���V���q�i�Q�V�@�y�P�V�ȁz
�@���K�R�̎R���t�߂̊��I�n�ɂ܂�ɂ��������Ȃ��B
�@�ʐ^�́A�R�[�̃z�e���ō͔|����Ă������́B
�@�@[�}�Ӈ@] |
 |
�@ |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�G�]�R�U�N���@�y�T�N���\�E�ȁz
��c�̗Z��n�ɑ傫�ȌQ��������B
���ԕi���V���o�i�G�]�R�U�N���Ƃ����B[�}�Ӈ@] |
�@200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�當��
�@�~�\�K���\�E�@�y�V�\�ȁz
�@���쌧�̖��X��i�ؑ]��̎x���j�ɐ�����
�@���Ƃ��疼�t����ꂽ�B�@[�}�Ӈ@] |
 |
 |
200�V�N7���P�P���@�B�e�F����@�@�r���R
�V���l�A�I�C�@�y�V���l�A�I�C�ȁz
�P�ȂP���P��̓��{���Y��B�Ԃт�̂悤��
������̂́A�ӕЂł���B�@[�}�Ӈ@] |
�@200�V�N7���P�P���@�B�e�F����@�@�@�r���R
�@�E�R���E�c�M�@�y�X�C�J�Y���ȁz
�@�E�R���́A�T���ŁA�Ԃ̑N�₩�ȉ��F����
�@���t����ꂽ�B�@ [�}�Ӈ@ |
 |
�@ |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�G�]�c�c�W�@�y�c�c�W�ȁz
������ƌ��������ł͑��̂悤�Ɍ����邪�A
������Ƃ����B
[�}�Ӈ@] |
�@200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�@�C���q�Q���G�]�c�c�W�@�y�c�c�W�ȁ��c�c�W�ȁz
�@�C���q�Q�́A�ꏊ�ɂ���āA�}�̑����A�Ԃ�
�@�傫���A�ԕt���̗ǂ��ȂǂŌ`�ԕω����傫���B
�@[�}�Ӈ@] |
 |
�@ |
200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�@�當��
���}�u�L�V���E�}�@�y�o���ȁz
���}�u�L�Ɏ��āA�t�́A�悪����ɂƂ���A
�t��(����)���͂����肵�Ă���B�@[�}�Ӈ@] |
�@200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�@�I�I�^�J�l�o���@�y�o���ȁz
�@���{�ƃ��[���V�A�k���ɍL�����z����
�@�i�^�J�l�o���́A���{�݂̂ɕ��z�j�B[�}�Ӈ@] |
 |
�@ |
200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�}���o�V���c�P�@�y�o���ȁz
��������̂悢�Ƃ�����D�ށB���Ԃō��n�ɐ�����
�i�V���c�P�͒W�g�F�̉ԂŁA��n�ɐ�����j�B�@
[�}�Ӈ@�A�F]
�@ |
�@200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�當��
�@�`�V�}�t�E���@�y�t�E���\�E�ȁz
�@�l�p�`�Ŏ��͎O�����h���тň͂܂�Ă���
�@��������u�ӂ����v�ƌĂсA�����ɐ����鑐
�@�i�엿�p�j���ӂ��두�B�u�O�����͂��Ă��āA
�@����������J���Ă���v�Ƃ����u�t�E���v�̃R���Z�v�g
�@�́A�t��(���C)�E�t�N��(��)�E�t�N���E(��)�E�t�E��
�@(���F)�Ȃǂɋ��ʂ���B�@�@[�}�ӇE] |
 |
�@ |
200�V�N7��7���@�B�e�F�ێR�@�@�@�@�當��
�J���t�g�Q���Q�@�y�}���ȁz
�Q���Q�́A�����Q�\�E�̐����a���B
�햼�̓Q���Q�����A�����̓Q���Q���łȂ�
�A�C���I�E�M���B�@�@[�}�ӇB] |
�@200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�@�V�R�^���\�E�@�y���L�m�V�^�ȁz
�@�V�R�^���́A�F�O���ł͂��߂č̏W���ꂽ
�@���Ƃɂ��B[�}�ӇD]
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@200�V�N7��8���@�B�e�F�ێR�@�@�@���K�x
�@�j�b�R�E�L�X�Q�i�[���e�C�J�j�@�y�����ȁz�@
�@�{���̖��O�́A�Z�b�e�C�J(�Z�b�e�C�̈Ӗ���
�@�u�������v)�܂��͂��ꂪ�Ȃ܂����[���e�C�J�B
�@�����ɐ����Ă���L�X�Q�̒��ԂƂ����Ӗ���
�@���O�ɓo�R�҂ɂ���ĕς����Ă��܂������A
�@���ۂ̓L�X�Q�̒��Ԃł͂Ȃ��B�@
�@[�}�ӇC] |
|
|
*******************************************************************
���F�P�D�Ԃ̖��O�́A�w�R�k�J���[���ӁE���{�̍��R�A���x�i�R�ƌk�J�Ёj�̂��̂��̗p�B
�i�@�j���́A���}�ӂł̕ʖ��@
���F�Q�D�}�Ӕԍ�
�@�@�@�@�@�@�@�w�R�k�J���[���ӁE���{�̍��R�A���x�i�R�ƌk�J�Ёj
�@�@�@�@�@�@�A�w���R�A���x�i���C��w�o�ʼn�j
�@�@�@�@�@�@�B�w��̉Ԃ����365���@��x�i�Z�p�]�_�Ёj
�@�@�@�@�@�@�C�w�R�k�J���[�K�C�h�@�J���[�R�̉ԁx�i�R�ƌk�J�Ёj
�@�@�@�@�@�@�D�w�k���A���̗��x�i�����V���Ёj
�@�@�@�@�@�@�E�w�A�����̗R���x�i�������Ёj
�@�@�@�@�@�@�F�w���̉ԂQ�x�i�R�ƌk�J�Ёj
|
|
��2007�N�V���@�k�C���̉ԁi�x�X�g�E�X���[�l�C���[�j�@����@���i���a31�N���j
�@�@�@�@�@������2007�N9��17���g�t�g�`�b���[�����]��
�@�w�R�̉ԁx�@���k�C�����@�u2007�N�k�C���̉ԁi���K�x�E�當���E�r���R�j�v�Q��
���g��@���v����i���a39�N���j�u�R�����g�v
�A���A���コ��̌Ăт����ŁA�x�X�g�E�X���[�̐l�C���[���s���܂����B�ȉ��́A���̌��ʂ�`���鍲�コ��̃��[���ł��B
�F����
���k�C���̉ԁA�l�C���[�̌l�ʓ���́A1�ʂ��珇��
�L�~�R�v�l�F �G�]�m�n�N�T���C�`�Q�A���u���E�X���L�\�E�A�n�C�I�g�M��
�{�ԁF �@�@�@�E�R���E�c�M�A�V���l�A�I�C�A�E���W���i�i�J�}�h
�g��U�߁F�@ �{�^���L���o�C�A���V���q�i�Q�V�A�G�]�R�U�N��
�ێR�F �@�@�@�G�]�c�c�W�A���u���E�X���L�\�E�A�}���o�V���c�P
�����F �@�@�@���u���E�X���L�\�E�A�G�]�J���]�E�A�E�R���E�c�M
�����F �@�@�@���u���E�X���L�\�E�A�E���W���i�i�J�}�h�A�E�R���E�c�M
����F �@�@�@�V���l�A�I�C�A�~���}�I�_�}�L�A�E�R���E�c�M
�����̌��ʁA
�����P�ʁF���u���E�X���L�\�E�i4�[�A10�_�j
�����Q�ʁF�E�R���E�c�M�i4�[�A6�_�j
�����R�ʁF�V���l�A�I�C�i2�[�A5�_�j�A�E���W���i�i�J�}�h�i2�[�A3�_�j
�c��9���1�[���ł����B
���ێR����A������̃{�^���L���o�C�̎ʐ^�͂Ȃ��Ǝv���܂��B���K�̒��ォ�牺�A���������̎Ζʂɂт�����J�[�y�b�g��ɍ炢�Ă��܂����B�ʐ^�ɂ͉������܂����B����8���ڕӂ�łP�A2�ցA���̘e�ɍ炢�Ă����̂ł����A���傤�ǂ��̎��A�O����������Ă����A�x�b�N�����������Ęe�ɂǂ����̂ł��B����ŏ����ʐ^���������Ĕނ��ǂ��z�����̂ł����A���̉��ɂ͂����o�����܂���ł����B�Ȃ��Ȃ����������̂���Ԃł������B
�ێR����A�h�N�^�[���c�ւ̎���ȂǁA�S�苭�������ɒE�X�B
����q
|
�y�l�C�x�X�g�E�X���[�̉ԁz�@�@���摜���N���b�N����Ɖ摜���傫���\������܂��B
| �@�@�@�@ �����P��******�@�@�@�@�@ |
�@�@�@�@�����Q��*****�@�@�@�@�@�@ |
�@�@�@�����R��*****�@�@�@�@�@�@ |
| ���u���E�X���L�\�E |
�@�E�R���E�c�M |
�V���l�A�I�C |
|
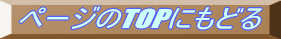
 |
��2009�N8���@���x�̉ԁ@�|���@���i���a39�N���j�@�����@�떾�i���a43�N��)������2009�N8��17�����e
�w�g�s�b�N�X�x�2009�N7��31���`8���Q���@�x�E���x�R�s�L��@�Q��
�E�E�ԂŗL���Ȏ��x�����A����˂������A�Ђ߂����A�������Ȃǂ݂͂ȏI�����
�����₵�������ł��������A�m���E�c�M�E�����������E�L���R�E�J�E�C���V���E�u�E�R�P�C�����Ȃǂ�����B
���킩���݂Ȃǂ͂��ꂩ��̂悤���B�E�E�@�ē��@���i���a42�N���j
�w�����R�s�x�2009�N7��31���`8���Q���@�z��V���[�Y��l�e�i�x�E���x�j��Q�� |
���G�f�V�����̋}�o�ł͖w�ljԂ������Ȃ��B���ꂩ�瑐��������A�Ԃ������Ȃ����B
���X�q��̑����̃j�b�R�E�L�X�Q�̌Q���͌����������B�q���T�����͏I����Ă��Ďc�O�B�i�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
 |
 |
2009�N8��2���@11:02�@�i�B�e�F�|���j
�����̗Ő��@�@�I�I�o�M�{�E�V |
2009�N8��2���@11:20�@�i�B�e�F�|���j
���x�ւ̗Ő���@�@�N�K�C�\�E |
 |
 |
2009�N8��2���@11:56�@�i�B�e�F�����j
���x����߂��̗Ő��@�@�L���R�E�J |
2009�N8��2���@12:59�@�i�B�e�F�����j
���x�`���G�X�q�̗Ő��@�@���}�u�L�V���E�} |
 |
|
2009�N8��2���@13:13�@�i�B�e�F�|���j
���G�X�q��̑����@�@�@�j�b�R�E�L�X�Q |
|
|
��2009�N8���@�x�̉ԁ@�����@�떾�i���a43�N��)�@�@������2009�N8��17�����e
�w�g�s�b�N�X�x�2009�N7��31���`8���Q���@�x�E���x�R�s�L��@�Q��
�@�E�E����P�T���A�뉀�̂悤�ȑ����̖ؓ����s���Ɛx���B�����������Ȃ�A
���̂�����q���T�����������Ȃ���͂������A���x���B�E�E�@�V���@���i���a42�N���j
�w�����R�s�x�2009�N7��31���`8���Q���@�z��V���[�Y��l�e�i�x�E���x�j��Q�� |
| ���O�x����ւ̎��ёт̋}�ȓo��ł́A�p�ɂɌ����c���A���h�E�V�̉��Ȕ����ԂƁA�c�o���I���g�̃����F�̎��ɈԂ߂�ꂽ�B�O�x����̑����̃L���R�E�J�̌Q������ۓI�B�i�����j |
 |
 |
2009�N8��1���@10:38
�l�Y���`���`�O�x����@�@�c���A���h�E�V |
2009�N8��1���@10:38
�l�Y���`���`�O�x����@�@�c�o���I���g |
 |
 |
2009�N8��1���@11:25
�O�x����@�@�@�^�J�l�j�K�i |
2009�N8��1���@11:26
�O�x���� �@�@�L���R�E�J |
 |
 |
2009�N8��1���@12:09
�x����@�@�^�e���}�E�c�{�O�T |
2009�N8��1���@12:43
�O�x������]�l�o�R���ւT���قlj���
�~���}�}�}�R�i: |
|
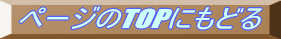
 |
��2009�N�V���@���R�n�̉ԁ@�|���@��(���a39�N��)�@�@�@�@�@�@�@������2009�N8��20�����e
�w�����R�s�x�2009�N7��9�`12���@�k�C���I�s�i�P�j���R�n�̉Ԃƒ���K�˂ģ�Q��
|
���k�C���I�s�ł̉Ԃ̎ʐ^�ɕt���ẮA�K�������s����ł̏o����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�I�s�ɋL�ڂ̂悤�ɁA7/9�̍��x���ӂ̃L�o�i�V���N�i�Q�A�E���W���i�i�J�}�h�A�n�N�T���C�`�Q�A�G�]�R�U�N���A�C���u�N���Ȃǂ̉Ԃ͎B�e�ł��Ă��Ȃ��A������7/10�̍��x����k�C�x�o�R���_�����ւ̓������A���V��ɑΏ����ĕ���i�߂�̂ɏW�����Ă������Ƃ�����A�ʐ^�͎B��Ă��Ȃ��B���ׂ̈ɑ����̎ʐ^��8/11�̒��ʊx�������A������A�H�ɎB�������̂��w�ǁB |
 |
 |
�����x�ւ̓r���ɂā@
2009�N7��9���@13:49
�E�R���E�c�M |
�����ʊx�����̋A�H�A�����P���ɂ�
2009�N7��11���@11:01
�G�]�i�J���t�g�j�C�\�c�c�W |
 |
 |
�����ʊx�����̋A�H�A�����P���ɂ�
2009�N7��11���@11:01
�C���u�N�� |
�����ʊx�����̋A�H�A�����P���ɂ�
2009�N7��11���@12:20
�R�}�N�T�Q���� |
 |
 |
�����ʊx�����̋A�H�A�����P���ɂ�
2009�N7��11���@12:36
�n�N�T���`�h�� |
�����ʊx�����̋A�H�A�����P���ɂ�
2009�N7��11���@12:36
�n�C�}�c���� |
 |
 |
�����ʊx�����̋A�H�A�����P���ɂ�
2009�N7��11���@13:30
�E���b�v�\�E�Q���� |
�����ʊx�����̋A�H�A�����P���ɂ�
2009�N7��11���@14:36
�G�]�m�c�K�U�N�� |
 |
 |
�����_�������ɂ�
2009�N7��11���@14:46
�L���|�E�Q�ƃG�]�m�n�N�T���C�`�Q |
�����_�������ɂ�
2009�N7��11���@14:50
�G�]�I���}�m�G���h�E |
 |
 |
�����_�����̐���ɂ�
2009�N7��12���@5:49
�����E�L���J |
���Ԋx���牺�R�H
2009�N7��12���@9:14
�G�]�R�U�N�� |
 |
 |
���Ԋx���牺�R�H
2009�N7��12���@11:30
�V���E�W���E�o�J�} |
���Ԋx���牺�R�H
2009�N7��12���@11:50
�G�]�C�`�Q |
|
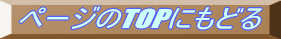

***** |
��2009�N�V���@�����A��̉ԁ@�얼�@�^��(���a62�N��)�@�@�@������2009�N8��17�����e
�w�����R�s�x�2009�N7��18�`20���@�����A��c����Q�� |
| ��7��18�`19���͈��V��̂��ߎʐ^���B�ꂸ�A20���݂̂̎B�e�B19���̈ȓ��x�ւ̓o��Ńq���T�����𑽐��������A�J�ɑł���ĉԂ͕��Ă����B20���̗Ő������ŁA�q�i�E�X���L�\�E�̌Q�����p�ɂɌ���ꂽ���A�P�T�ԑO�ɉԂ��I����Ă��Ďc�O�B�@�@�@�@�@�@�@*******�����s���������i���a43�N���j�̕⑫ |
 |
 |
���ȓ������`�ό�����
2009�N7��20���@6:32
�~���}�N���}�o�i |
���ȓ������`�ό�����
2009�N7��20���@6:34
�E���W�����E���N |
 |
 |
���ȓ������`�ό�����
2009�N7��20���@6:37
�C�u�L�W���R�E�\�E |
���ȓ������`�ό�����
2009�N7��20���@6:44
�g�L�\�E |
 |
 |
���ό������`���召��
2009�N7��20���@8:48
�^�e���}�����h�E |
���ό������`���召��
2009�N7��20���@8:53
�n�N�T���C�`�Q�@ |
 |
 |
���ό������`���召��
2009�N7��20���@9:00
���c�o�V�I�K�} |
���ό������`���召��
2009�N7��20���@10:14:
�G�����C�\�E |
|
|
|
|
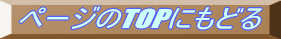

�@�@�@ |
|
|

